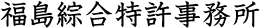化合物特許(物質特許)をマーカッシュクレームで記載する際の「難しさ」は、弁理士・研究者双方にとって独特の課題があります。いくつかの観点に整理しますね。
1. 構造の網羅性と適切な限定のバランス
網羅性
マーカッシュクレームは「A¹がハロゲン、アルキル基…である化合物」といった形で広く記載できますが、広すぎると新規性・進歩性で既存文献に引っかかりやすいです。
限定の適切さ
逆に狭すぎると権利範囲が小さくなり、類似化合物に迂回されやすい。つまり、発明の効果を維持しつつ、先行技術に重ならない「ちょうどよい広さ」に調整することが非常に難しいです。
2. 実施可能要件・サポート要件
日本・米国・欧州などいずれの国でも、クレームで列挙した膨大な化合物群のすべてが実施可能であることを示す必要があります。
実験例は数個でも、請求範囲が数百万通りに及ぶ場合、「本当に全部効果があるのか?」というサポート要件の問題が出ます。
特に近年は欧州(EPO)や日本でもサポート要件の審査が厳しく、単に「数種の実施例」だけでは不十分となる傾向があります。
3. 構造と効果の関連付け
効果(薬理活性・物性など)と構造の対応関係を合理的に説明することが求められます。
例えば「置換基RがC1–C6アルキルの場合に抗菌作用が強い」などの**構造活性相関(SAR)**を示し、広いマーカッシュ群に正当性を与える必要があります。
これを欠くと「広すぎて発明の課題解決が担保されていない」と拒絶されます。
4. マーカッシュ表現の複雑性
「R¹はハロゲン、アルキル、アリール;R²は…」という形で階層的に展開すると、請求項の文章が非常に複雑になります。
誤記、抜け漏れ、整合性欠如が生じやすく、拒絶理由や無効理由に直結するリスクがあります。
特に米国出願では、マーカッシュのクレーム解釈が日本や欧州と異なる場合もあるため、国際出願では調整が必要です。
5. 先行技術調査の困難さ
既存化合物の公報が膨大であり、わずかな差異で新規性が否定されることもあるため、検索が難しい。
特に構造検索・Markush検索を専門的に行わないと、見落としやすいです。
その結果、「想定外の先行例に潰される」リスクが高い分野です。
6. 実務上の落とし穴
クレームの過剰複雑化 → 読み手(審査官・裁判官)に理解されず、無効リスクが増す。
翻訳リスク(PCT→各国移行時) → 「R基の定義」が訳文でずれ、サポート要件違反や不明確拒絶を招く。
権利化後の行使難易度 → 侵害品との同一性判断で、「マーカッシュ群に入っているのか」を立証するのが難しい。
✅まとめると、化合物特許の難しさは
広さと限定のバランス
サポート要件の厳格化
構造と効果の因果関係の立証
マーカッシュ表現の複雑性と翻訳リスク
検索・侵害立証の困難さ
これらが重なり、特許実務の中でも最難関の一つとされています。
25年以上、有機化学に関わり、化学研究者、特許庁審査官、弁理士、大学知財部などを経てきて、化合物の記載方法が、理解できたのは、とても自分の武器になっています!